古利根川の遺物・高道
地震・雷・火事・親父とは、日常、人々の恐れるものを、その順に列挙していう語であるが、今日の世相では「親父」の代わりに「17歳」が通語のようだ。しかし、親父や17歳は天災ではないし、他語との共通性に欠ける。本来なら、地震・雷・火事・台風がよい、と勝手に考えている。2000年9月11日、台風14号は東海地方に豪雨をもたらし、静岡で617ミリ、名古屋で562ミリを記録した。丘陵の多い静岡県には、富士川、安倍川、大井川、天龍川の四つの大河が流れている。これが豪雨を呑み込んで海へ流した。被害は意外と少なかった。一方、名古屋では新川が決壊し、大量の泥水が多くの家を襲い、床上浸水が多く出た。
テレビの映像では、新川は大河ではなく、人工の手が入った直線的な天井川(河床が周囲の平野面より一段と高くなったもの)である。川の周囲は、かつては田畑であった新興住宅地のようで、起こるべくして起こった災害である。
2000年7月9日、わが春日部市も台風3号の暑中見舞いを受けた。異常気象である。春日部市の雨量は181ミリ、台風特有の断続的強雨であったが、市の道路は各地で冠水した。杉戸から 春日部の牛島へ流れる倉松川は各地で被害を出し、古利根川も氾濫しそうなところもあったとか。
春日部も名古屋同様、昔は海の沖積地。古利根川の標高は約5メートル、川の勾配は6000分の1、60mで1cm低くなる割合である。ひとたび洪水になると、名古屋のように水の引くのが遅い。水たまりになる。
皮肉なことに、この緩やかな勾配が古利根川を濫流蛇行させ、この川を介して上流からの大量の土砂を運び、堆積させ、今日の春日部を形成したのである。
古利根の流れが生んだ
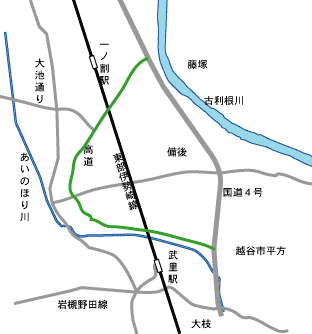 |
一ノ割駅を降り、武里方向へ線路沿いの道を300mほど行くと、二つ目の踏切がある。この踏切を横切る道が、通称「高道」(たかみち)と地元育ちの人が呼んでいる道である。
私ら外様住民は、30年近くも生活していて、この道が高道であると知ったのは、つい最近のことであった。この道、幅は数mであるが、古利根川が造った高さ1メートル、幅100mを超す砂丘の上部を通っている。そして半円を描くように、踏切手前の備後香取神社付近から、備後須賀稲荷神社前を通り、相之堀川に沿って武里方面へ伸びている。かなり古い時代にできた砂丘のようで、その証として鎌倉時代から江戸時代にかけての社寺や、古木の小さな自然が混成した屋敷林を持つ大きな農家も、この砂丘の上には多い。この高道と平行するように、一ノ割駅付近から一ノ割香取神社、円福寺、相之堀川へと、高道同様、高さ1m、幅100mぐらいの砂丘が伸びている。この砂丘を江曽(えぞ)堤という人もあり、この砂丘上にも高道のような道が走っている。
この両道の間は約300mの狭間となっており、中ほどは船底のように1mほど低い。江戸時代の初期まで、古利根川はこの低いところを流れていた。両側の砂丘は古利根川が造った自然堤防の痕跡である。
この辺りの地名には出土(出戸から変化した地名で、川の出入り口か、土の山ている砂州?)、西川、上川、下川、島野谷、須賀島(スカとは、砂地のことをいう)など川に因んだ地名が多い。
私のマイホームは島野谷。川の底で昔は田植えにも苦労する深田。豪雨が三十分も続くと、家の前の道路は坂を下る水が用水(今は下水)に押し寄せ、そこから噴き出した水で冠水する。家を建てるとき、1mぐらい下駄を履かせればよかったと後悔している。
さて、このさすらいの古利根川。どこへ流れていたのであろうか。古利根川が新方袋を通っていたころ元荒川と合流し、溢れた水が一ノ割方向へ流れ込んだという説もあるが、昔の地図や航空写真から考察すると一ノ割から高道に沿って武里の大畑大枝、大沼、山谷、船渡あたりをうろつき、さまよったような気がするが、いかがであろうか。
昭和22年9月中旬、関東地方はキャスリン台風の襲来を受けた。栗橋で利根川の土手が決壊し、濁流は秒速5mの速さで幸手町などを呑み込んだ。古利根川も全線にわたり溢水氾濫、2戸の家屋が流失、水死者も2人出た。
水防団が備後の土手500mに3000俵の土嚢を3〜5段に積んで防いだが、越水決壊した。そのとき、半円状に囲まれた高道の内側と古利根の元川底の地は、4号国道を乗り越えてきた濁流に浸かった。
でも、高道などの砂丘上には被害はなかった。記録では、円福寺で252人、武里小牛校で56人、大場の光明寺で50人の被災者を収容している。昔から寺社は高い場所に建立していたのである。
当時、水害にあった土地は今では人家でびっしり。シトシトピツチャン型やチンタラ雨なら何日続いてもへっちゃらだが、300mm以上の集中豪雨を受けると、春日部市も名古屋の二の舞になる気がする。
川には、削る、運ぶ、堆積させるの三作用がある。そして、大雨のときは猛烈なエネルギーを出す。エネルギーの方程式は、流速の6乗である。速さが10倍になれば、エネルギーは実に100万倍にもなり、巨石でも簡単に運ぶ。
昨年、玄倉川では、中洲にテントを張って野営した人々が濁流に呑み込まれ、命を落としたことは記憶に新しい。水力を侮ってはならない。
しかし、この三作用のエネルギーが、われわれの住む土地を造ってくれたのも事実である。
春日部は文字どおり、川の町である。元荒川、古利根川、庄内古川の3本の大河にかかわっている。いずれも「元」や「古」のつく、かつての幹流である。特に古利根川は群馬県の利根川の水を、庄内古川は渡良瀬川と栃木の思川の水を東京湾へ運んでいた。それにしては、この両川、上流の水量を考えると、幅100m以下であまりにも狭い。まして昔はダムがない。
……では?そうです。この両川、流域の原野に大量の水を垂れ流して、各所に沼や湿原を造っていた。そして、湿原や沼は東京湾まで続いていたのである。これらの川が今日のようになり、新田が開拓され始めたのは徳川葵三代以後である。
関東平野は、過去二百万年の間に400m沈降した。沈降速度に逆らって穴埋めをしていたのが、これら河川である。
歴史を見ても、川は100年に1回は大氾濫を繰り返し、流れを変え、土砂を運んできた。200万年では2万回も氾濫したことになる。砂丘や高道のような川の働きでできた微高地はかなりあったが、今日では工事で姿を消したものも多い。
さて、みなさん。自分の住んでいるところはいかがですか。地名なども参考になります。でも、千間台のように根拠のない地名もあります。家を建てるときには、ご注意を。(※高道については、次の方々のお話を参考にしました。ありがとうございました。文化財保護委員 石川善郎氏 市議会議員 石川良三氏)《あみゅーず86号(2002年9月)より転載》
|